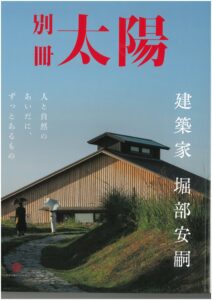「京都の木の家」「注文住宅」の竹内工務店ブログです。
京都市左京区の閑静な住宅地で、「F邸」の建て方が行われました。
東西に奥行きのある敷地に母屋と離れで構成されたお住まいです。
「建て方(たてかた)」は、木造建築において大工工事が始まる節目でもあります。
基礎の上に土台、柱や梁を組み上げ、建物の骨格が一気に姿を現す瞬間は
図面で描かれていた家が、実際の空間として立ち上がるダイナミックな工程で
最後に棟木を上げて棟上げとも言いい家づくりの特別な場面です。

東西に奥行きのある敷地での計画です。
建て方は、まず敷地の奥から始まり、順番に手前へと進めていきました。
建物の規模が大きいため、通常よりも建て方の日数がかかり、大工さん5人で4日の工程となりました。
下の写真は基礎に土台が乗った状態です。

朝から何便かに分けて木材が現場に搬入され、着々と組み上がっていきます。
大工さんにとっては力仕事の連続であり、同時に気の抜けない緊張の場面が続きます。
胴差と床梁を一つひとつ、慎重に組み上げていきます。

大きな木材を納めるために「掛矢(かけや)」と呼ばれる大きな木槌を使い、力強く叩き込んでいきます。
木を打つ音が響き渡り、木と木がぴたりと組み合わさる様子は、見ていても気持ちのよい瞬間です。

建て方がスタートして4日目、建物の骨組みが見え
無事に上棟することができました。
F様 この度は誠におめでとうございます

竹内工務店の家づくりでは、土台や柱や梁といった骨組みになるべく無垢材を使用しています。
今回のF邸では、大きな梁などは一部松の集成材を使用していますが、その他土台は桧、柱は杉です。
構造材は家が完成するとほとんどが見えなくなりますが、
しっかりと乾燥させた無垢材は、強度が高く耐久性にも優れていますし、
木は呼吸する素材なので、空気中の湿度を調整し、家全体が快適な空気環境となります。
今、現場は木の香りに包まれています。

登り梁は化粧現しとなりますので、傷かつかないように気を付けて組み上げています。

母屋の屋根の梁の一部は、複雑な形状のためプレカット加工できずに大工が手刻み加工をしています。

今後も現場の様子などお伝えしますのでお楽しみに!
設計は高橋勝設計事務所さまです。
以前に施工させていただいた設計は高橋勝設計事務所さまの新築注文住宅の施工例はこちらをご覧ください
京都市右京区「北嵯峨の家(O邸)」